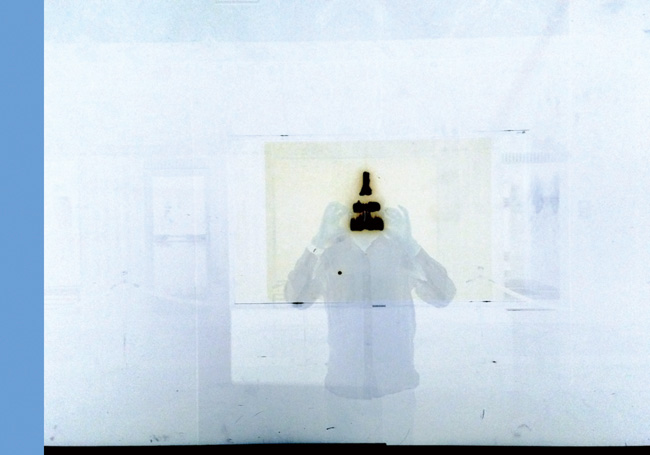
<スケジュールに関するお知らせ>
2014年3月に開催された3331 ART FAIRにて選出されたアーティスト、蓮沼執太による個展を開催します。
蓮沼執太は1983年東京都生まれ。音楽作品のリリース、コンサート公演、映画、舞台芸術、音楽プロデュースなど幅広いフィールドで活躍する音楽家として内外で高い評価を受ける気鋭の作家です。豊かな音楽性で幅広い層からの支持を得る一方で、作曲の手法を様々なメディアに応用し、映像、サウンド、立体、インスタレーションの制作にも取り組み、個展形式での展覧会やプロジェクトを活発に行っています。
本展覧会では、新作のインスタレーションを発表します。展示空間に音響的彫刻をインストールし、観客の存在/不在といった環境因子によって音響を変容させる、現象を作曲する試みです。
2014年ではアジアン・カルチャル・カウンシル(ACC)での招聘にてニューヨーク滞在から帰国しての初めての個展となります。2015年5月に開催予定の個展『作曲的|compositions - space, time and architecture』(国際芸術センター青森(ACAC))、7月開催予定の国際展別府現代芸術フェスティバル2015「混浴温泉世界」での出展も決まっており、新作発表が続きます。その第一弾としての本展『知恵の処方|Prescription for Coactivity』での新たな手法をご覧下さい。
----
五感を刺激する庭
武満徹に『時間(とき)の園丁』と題する著書がある。音楽家の書物にこれを凌ぐ題名はないのではないか。『シザーハンズ』のジョニー・デップよろしく、ざっくざっくと音を刈り込み、刻み、整える作曲家の手業が目に浮かぶ。
蓮沼執太には志村信裕と協働した「時間の庭」というライブイベントがある。たぶん先達へのリスペクトを込めた命名だろうが、いずれにせよ「園丁」や「庭」は蓮沼作品にもふさわしい修辞に思える。時が奏でる、そして僕らも奏でる。「僕ら」の介入によって「時」はわずかに、だが決定的にその様相を変える。
同様に、庭師・蓮沼が展覧会という庭の造園を手がけると、植物や昆虫(アート作品)から成る生態系は確実に活性化される。
庭に迷い込んだ我々も大いに五感を刺激されるに違いない。
小崎哲哉(『REALTOKYO』『REALKYOTO』発行人兼編集長)
----
----
当初、私は展覧会のタイトルを『No Music was Playing』にしようと考えていました。古い時間と新しい時間の接続が主題でした。それは今も変わらないのですが、そこへふと、ルーマニアの思想家エミール・シオランの短文を思い出しました。
われわれは、時間にゆっくりと押しつぶされるよりは、時を追いこし、刻々の時にわれわれの時間を加えるほうがましではないかと考えた。この、古い時間に接木された新しい時、練りあげられ、計画された時は、やがてその有毒性を暴露しようとしていた。時は、自己を客観化しながら、歴史、すなわち、われわれ自身が自分の前に打ちたてた怪獣から脱れることのできない宿命となろうとしていた。それに対して受身の態度や、知恵の処方は何ものもなしえなかった。
『自己に反する思考』
我々に潜在する時間感覚を共活性、すなわち人間とそれ以外の総て、地球の総体を比較する実験を試みました。その方法は無限にあって構わないでしょう。
*『知恵の処方|Prescription for Coactivity』について
"coactivity" を "知恵" と翻訳しました。co-activity=共活性。またはサイエンスの領域だと、同時活性化、という意味が近しいでしょうか。
蓮沼執太
----
蓮沼執太『知恵の処方』によせて
畠中 実
かつて蓮沼執太は、初の大規模な個展となる『音的|soundlike』(2013年)の開催にあたり、その一年前からその会場で毎月一回開催されたリサーチおよび仕込みのためのイヴェントを「蓮沼執太のスタディーズ」と名付けていた。そう思うと、蓮沼の表現において、展示という形態をとるものには、どれもどこか「スタディ」(習作)と呼ぶのがふさわしいところがある。
誤解のないように付け加えるなら、それは、完成された作品ではないというような意味ではなく、蓮沼が音楽家であり、主たる表現手段が音楽であるということに由来するのだろう。また、蓮沼自身もそうした展示作品を、音楽家による美術表現というよりは、音楽のための「スタディ」と位置付けているように思えるからかもしれない。あくまでも、展示としての作品発表が、音楽家の表現の範疇にあるものだというスタンスは、私も参加した「スタディーズ」でも、蓮沼の制作態度としてたしかに感じ取ることができた。その意味で『音的』とは、展示という表現形態において音楽の展開方法を試行するための、音楽の別名であり「スタディ」だったのだ。
それはまた、音、映像、演劇、などあらゆるものをコンポジション=構成としてとらえなおす試みでもあった、と言うことができるかもしれない。その時点では、音的なものを構成し配置することが、すなわち作曲=音楽的な行為となり、そうした経験が、蓮沼の音楽をアップデートする契機となる、という関係にあったということだろう。そのようにして作られていった一連の作品は、蓮沼のスタディ(研究)の成果をよく表している。
この『知恵の処方』は、蓮沼によるインスタレーション展示である。銅板で加工された、集音のための大きな喇叭が、それほど大きくはない展示空間いっぱいに拡がるように、直立する流木のような構造体から、枝が伸びるように三方向を向いている。これが、この作品の造形的要素である。それは、蓮沼のこれまでの展示の中でも、造形的な要素が強く出ていると思われる。喇叭状の集音器の中にはマイクが取り付けられていて、ほぼその先にはマイクから入力された音が出力されるスピーカーが設置されている。マイクのケーブルは、複数のエフェクターへと接続されて、入力される音は加工、変調をへて、アンプで増幅され、スピーカーから出力されるようになっている。これがこの作品の基本的なシステムである。
会場には特別にインストラクションがあるわけではない。作品はいわばシンプルな音の入出力システムとなっており、それ自体では音を発することはなく、作品固有の音というものも持っていない。ある人は、音が聴こえない、あるいは音のない作品、オブジェのようなものと思うかもしれない。このような作品を見慣れた観客は別にして、おそらく、何も起こらないことにしびれを切らした観客は、作品を一巡したくらいののちに、おもむろに音を発し始める。手を叩いたり、声を発してみたり、展示空間の中でなんらかの発音行為に駆り立てられるかもしれない。その音はエフェクターとアンプを通過して空間内に大きな音を響かせる。その音はふたたびマイクへと入力され、数秒前に発された音は、マイクとスピーカーの間を循環する。ここでは、空間の音響特性も作品の要素のひとつであり、音の発された状況によって、音の行方がさまざまに分岐していく。フィードバックという現象を完全にコントロールすることは不可能だ。
一方、そこに音が起こらなければ、その装置は反応することがないかといえば、そうでもない。たとえば、会場の扉を開けて誰かが入ってくるとき、あるいは出て行くとき、作品は突然咆哮するような音をたてるかもしれない。予測不可能な音響生成装置というべきか。それは、空間、観客、そして時間によって、ある場を生成する。耳を音の時間の経過に伴う変化にゆだね、それに促されるようにして次の音の元をひとつひとつ、その装置に与えていく。そこには、装置と観客とのフィードバックによって、つねに変化していく音楽的なものが生起する音響装置が構想されているのかもしれない。
畠中 実 NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員
----
協力:NO ARCHITECTS
当サイトには、入居している各団体が行う催事についての情報も掲載されています。
展覧会やイベントなどに関するお問い合わせは、各団体へお願い致します。